
OPINION PAPER No.36(25-002)
2025年大阪・関西万博における情報空間設計の検証
:デジタル体験と情報格差の視点から
1. はじめに:物理空間と対をなす「情報空間」の設計課題
2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、大屋根リングに象徴される革新的な物理空間設計で注目を集めた。その成功には、建築や展示といった物理空間の設計に加え、チケット購入から来場、パビリオン予約、移動、決済に至るまで、来場者が情報端末を介して体験する情報空間の設計が不可欠であった。
今回の大阪・関西万博では、来場予約・入場システムをはじめとする各種手続きのDX(デジタルトランスフォーメーション)化が徹底された一方で、その情報空間設計に起因する複数の課題が顕在化した。本稿では、情報空間設計を物理空間設計との対比の中で検証し、特にデジタル体験と情報格差の質に焦点を当て、今後の大規模イベントにおける情報システム設計への教訓を考察する。(*1)
2. 「情報を制する者が万博を制す」:情報格差と機会の不平等
大阪・関西万博におけるパビリオンやイベントへのアクセスは、基本的に公式ウェブサイトを通じた複数の予約経路(2か月前抽選、7日前抽選、3日前空き枠先着予約、当日登録等)(*2)に大きく依存した。この多段階的な予約システムとデジタルチケットサイトへの一元化は、実装上の“速度競争”が生じやすい状況を招き、結果として情報格差が体験機会の不平等として顕在化した。
来場者は、端末・回線速度・操作スキルを駆使して希望の予約枠獲得を競うことになった。実際、先着開始の瞬間にはアクセスが殺到し、運営側は負荷平準化のためウェブ上に「待合室」機能を設けたが、混雑時には長い仮想待機列が発生した。結果として、「時間(深夜0時開放等)と端末操作の機動性」が希少な資源として機能し、万博の来場体験は、事実上「情報戦」の様相を呈した。
2.1. 事前予約における情報リテラシーの優位性
特に先着予約の段階では、公式では案内されていない予約ウェブサイトの待機列回避方法や、ブラウザのCSSを改変することによって予約枠を確保しやすくするといった、非公式に共有された手順やノウハウが、インターネット上のコミュニティやSNS、技術系ブログを通じて広く拡散された(*3)。
これらの非公式情報にアクセスし、ある程度のPC知識をもって実行できた人々が予約において優位となった事実は、情報通信技術の利用能力の差が社会的な機会の格差を生むデジタルデバイド(情報格差)の事例として捉えられる。運営側は自動化されたアクセスを試みるユーザーを排除する措置を講じたが(*4)、予約システムの設計自体が情報リテラシーの高い層に有利に働く構造だった可能性は高く、結果として機会の不平等を招いたと考えられる。
2.2. 当日来場後の「デジタル労働」
情報戦は、当日来場後も継続した。入場10分後から当日登録が可能となり、人気パビリオンの当日枠が会場内で逐次開放されたためである(*5)。これにより、来場者は、当日枠の獲得を狙いスマートフォンで更新を繰り返すか、当日登録を諦めて予約不要の館やスポットを回るかという選択を迫られた。その結果、「万博会場には入れたが、人気館の予約は取れず入場できなかった」という感想も少なくなかった。
当日枠の獲得を求める来場者は、スマートフォンを握りしめ、ウェブページを繰り返しリロード・クリックし続けることとなった。これは、希少な体験機会を得るために来場者が行う、時間と労力をかけた非報酬の活動である。社会学的な文脈では、この行為は「デジタル労働」(*6)とも呼ばれる。万博という非日常的な文化体験の場で、「リロード競争」というデジタルのストレスが生じやすい設計であったことは、情報空間設計が来場者の体験負荷を増大させたことを示唆する。
3. デジタル体験の質の課題:接続性、危機管理、包摂性
情報空間設計は、予約システムだけでなく、会場内のインフラとしての安定性にも責任を負う。
3.1. 不安定な接続環境と体験の阻害
今回の万博では、来場者に対して公式に「通信不良や電池切れのトラブルなどに備えて、QRコードを印刷したり、スクリーンショットで保存して持参することもできます」と推奨された。この推奨と複数のメディアレポートを総合すると、会場内における通信環境が、DX化されたシステムを支える公共インフラとして十分な安定性を持っていなかった可能性が示唆される。
入場やパビリオン観覧にQRコードの提示が必須であるにもかかわらず、「ネットがつながらない場合に備える」必要があるという事実は、情報空間の安定性・信頼性に対する根本的な懸念を浮き彫りにした(*7)。物理空間における安全基準が生命と安全を守るのと同様に、情報空間における「確実なアクセスと利用の保障」は、体験の土台として不可欠である。
3.2. 危機時における情報導線の機能不全
開催期間中の2025年8月13日夜に発生した大阪メトロ中央線の電気系統トラブルによる運転見合わせによって、多数の来場者およびスタッフが万博会場から帰宅困難の状態に陥った。主催者は翌14日にかけて危機対応を行い、謝意とともに情報提供・一時滞在施設・飲食提供の改善課題を公表した(*8)。大阪メトロの事後報告では、当時中央線での帰路予定者は約3.8万人と推計され、振替・臨時バス等での代替輸送が実施された(*9)。
本事案は、交通インフラの途絶という物理的な問題が、情報伝達の「導線」の脆弱性を露呈し得ることを示した。交通インフラの途絶という危機的状況下において、退出・代替動線の即時提示(アプリやプッシュ通知、サイネージ、巡回アナウンス等)と情報の一斉周知UI(ユーザー・インターフェース)を標準化することは、次の大規模イベントに向けた必須の改善要件である。
3.3. キャッシュレスとKANSAI MaaSの包摂性
会場内は国際博覧会として初の全面的キャッシュレス(*10)が導入され、約70種類の決済ブランドにくわえて公式のデジタルウォレット等の決済手段が用意された(*11)。また、交通連携のためのKANSAI MaaSが整備され、近隣の主要駅から万博会場に運行されるシャトルバスの予約・決済をアプリで一元化した(*12)。これらのDX化は、利便性の向上という点で評価できる。
しかし、この徹底したデジタル化は、キャッシュレス決済に不慣れな層やデジタルデバイスを持たない、あるいは使いこなせない層にとって、支払いや移動といった体験の根幹部分でデジタルデバイドの溝として横たわる可能性を内包していた。利便性の追求が包摂性とのトレードオフを生んだ点は、情報空間設計の検証における重要な論点である。
4. 物理空間設計と情報空間設計の比較検証
万博会場全体の空間設計やパビリオン内の動線設計は、2020年12月に策定された「基本計画」(*13)に示された基本方針、すなわち「非中心・離散」の理念と、それを「つながり」で重ね合わせた「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインコンセプトに基づき、極めて高い品質基準が設定された。
そして、この高い品質基準は「基本計画」の「5.4 会場整備」において、来場者の「安全かつ快適な万博体験」を確実に提供するため、「デザイン性(美しい会場)」「機能性(使いやすい会場)」「ユニバーサルデザイン」「環境配慮・暑さ対策」といった多角的な配慮を全ての施設に求めている。具体的には、国・地域、文化、人種、障がいの有無等に関わらず世界中の人々が利用しやすいユニバーサルデザインの実現を明確に目指し、また、大屋根リングや日除けの適切な配置による暑熱環境改善も計画の根幹に据えられた。
しかし、この物理空間の設計思想が追求した「誰にとっても公平な快適性」と「多様な人々の包摂」という原則は、情報空間の設計、特にパビリオン予約システムにおいて十分に連携していなかった。この課題の根源は、物理空間と情報空間、二つの「会場」を設計する上での根本的な設計思想の非連携にあると本稿は考える。
- 物理空間設計の視点:
- 公平性: 建築基準やバリアフリー法に則り、炎天下対策、混雑緩和のための広場・動線の確保、災害時の避難計画等、誰にとっても公平な「安全・安心」の基盤を設計する。
- 制約: 敷地面積や建物容量といった動かしがたい制約を前提に、混雑対策等の最適解を探る。
- 情報空間設計の課題:
- 公平性: デジタルスキルや情報収集能力の差が、特定の体験へのアクセスを左右し、公平性の担保が困難となった。
- 制約: 情報空間は物理的な容量の制約は小さいが、アクセス集中によるサーバー負荷という新たな制約を生む。この「仮想的な制約」に対する設計(例えば公平な予約枠の割り振り、安定した接続環境の提供)が不十分であった。
物理空間設計が、計画の理念に基づき「誰でも・安全に・質の高い快適性をもって・来場できる」ことを基本原理とするならば、情報空間設計もまた「誰でも・公平に・情報にアクセスし、体験の機会を得られる」ことを基本原理とするべきである。今回の情報空間設計は、この後者の原理において、アクセシビリティと公平性の観点から十分にデザインされていたとは言い難い。
人気パビリオンの入場において「最大6時間待ち」(*14)という過酷な物理的ストレス(機会獲得のための時間的投資)と、予約のためのリロード競争という過酷なデジタルのストレス(機会獲得のための技術的/時間的競争)が存在したことは、「体験機会の希少性」という課題が、物理空間と情報空間という二つの場で、来場者にとってのストレスとして異なった形で顕在化したことを示唆する。この結果は、両空間の設計が有機的に連携し、来場者体験全体を最適化する視点が不足していたことを示す。
さらに、情報空間の不平等に加え、混雑度の高い日や時間帯における物理的ストレス(猛暑、長時間の待機列等)は、暑さ対策や給水確保等の装備、体力、前泊の可否といった経済力や体力に裏付けられた個人的リソースを持つ来場者に有利に働き、物理空間における機会の不平等も並行して生み出したと考えられる。
一方で、こうした主催者側による情報空間設計の課題に対し、市民コミュニティから自発的な「補完」活動が生まれたことは注目に値する。例えば、一般市民が公式よりも利便性の高い会場マップを作成し、SNSでのフィードバックを反映してアップデートを重ね、無料で公開するといった草の根の取り組みである。(*15)
このような市民参加型の情報生成は、万博を「自分ごと」として捉える機運を醸成し、結果的に万博体験の質を(非公式な形で)底上げする一助となった。これは、主催者側が提供する「公式の情報空間」の課題を、ユーザーが主体的に改善した事例であり、市民参加の観点からは評価される側面である。
しかし同時に、本来は主催者が「ユニバーサルデザイン」の一環として担保すべき情報アクセシビリティを、市民の自発的な「デジタル労働」が補完したという事実は、公共インフラとして主催者が提供すべき情報の範囲と、市民参加による自発的な情報生成との適切なバランスや協働のあり方を、今後の大規模イベント設計において模索していく必要性を提示した。
5. 結論:次世代の万博に向けた情報空間設計の教訓
2025年大阪・関西万博は、デジタル技術を全面的に導入した未来志向の試みであった。しかし、本稿が示した通り、情報空間は、来場者が利用し、体験を構築する「見えない建築」である。予約・決済・移動・鑑賞へと連続するこのデジタルな空間は、単なる技術的なシステムとしてではなく、公共インフラとしての規範に基づいて設計・運用・検証されねばならない。
複数の予約経路(抽選、先着、当日枠)が設けられた背景には、アクセス機会を多様化させ、来場者の動機付けを高める設計意図が想定される。しかし、結果として、この複合的な予約システムは、抽選の平等性よりも、デジタル技術リテラシーに基づく競争を誘発し、機会の不平等を助長した。システムの意図(多様な機会提供)と結果(情報競争の激化による格差の助長)の間に乖離が生じた点は、今後のインターフェース設計における重要な教訓である。
また、大阪・関西万博では、オンライン空間上に夢洲会場を再現した「バーチャル万博」も用意されたが、これが混雑問題の緩和にどれだけ実質的に貢献したかは明らかではない。むしろ、物理的な会場へのアクセスが困難な来場者への機会提供という側面はあったものの、万博が「物理的な来訪体験」に価値の核心を置いている限り、「会場に来る意味」を希薄化させかねないという根本的な矛盾を抱えることとなった。これは、情報空間が物理空間の代替となり得ない、あるいは代替となればなるほど万博自体の存在意義が問われるという難しさを示唆する。
今後の大規模イベントの情報システム設計においては、以下の三点を最優先で取り組むべきである。
- 公平性の確保: デジタルスキルや情報アクセス能力に依存しない、すべての人に開かれた公平な仕組みを設計する。抽選機会の多様化や、アナログな代替手段の用意は「誰もがアクセスできること」を最優先の原則とする。
- 包摂性と安定性の確保:情報インフラを生命線と捉え、会場内の通信環境やサーバー負荷対策を物理的な構造物と同等の堅牢性で設計する。また、キャッシュレス等のDX化は、デジタル弱者を排除しない包摂性を重視する必要がある。
- 統合的デザイン:情報システムを、物理的な混雑やストレス(待機、猛暑)を緩和し、来場者体験全体を向上させる「人間中心のツール」として位置づけ、物理空間設計と統合する。特に、危機管理時における情報導線は、物理的な動線・避難計画と同等の重要性を持ち、デジタルとアナログの双方からの多重化と説明責任が不可欠である。
未来社会をデザインする万博の教訓は、情報技術が、一部の優位な層のためではなく、すべての人々の体験を根本から向上させるためにこそ使われるべきであるという、情報空間設計の公共性と倫理を強く訴えかけるものとなった。
註・参考文献
*1 本稿では、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会を「主催者」、主催者が公表した文書・ページを「公式」、会期中の現場運用(主催者・委託・関連事業者)に関わる組織全体を「運営側」と呼ぶ。
*2 予約は「EXPO2025デジタルチケット」サイト上で万博IDに紐づいて行われ、2か月前抽選、7日前抽選、3日前空き枠先着予約(来場日時予約をした日の3日前から前日の午前9時まで受付)、当日登録(入場10分後から)といった多段階的なシステムが設定された。詳しくは大阪・関西万博「予約・抽選ガイド」を参照。https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/reservation/(最終確認日:2025年10月31日)
*3 SNS・個人ブログ・note等でCSSフィルタやルート直打ちの手法が多数共有された。2025年10月31日時点で確認できたものとして、https://kamome-trip.com/expo-reservation, https://skypenguin.net/2025/05/24/post-106170/, https://theshow-jp.com/expo2025-reserve-pc/, https://motoryokoblog.com/?p=2895等がある。
*4 会期中には当日登録(先着予約)を目的とする自動で過度なアクセスが発生し、運営側は万博ID/チケットIDの利用停止で対応した(2025年8月28日公表)。https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250828-02/(最終確認日:2025年10月31日)
*5 大阪・関西万博「よくあるご質問:【パビリオン・イベント予約】「当日登録(予約)」について教えてください。」https://faq.expo2025.or.jp/hc/ja/articles/4735482963998(最終確認日:2025年10月31日)
*6 Tiziana Terranova, 2000, “Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy,” Social Text, 63(Vol. 18, No.2), pp.33-58.
*7 QRコードについて、大阪・関西万博公式ウェブサイト上では「スクリーンショットをとっておくと便利!」や「事前にQRコードを印刷してもっていくと安心!」と明記され、スクリーンショットや印刷をすることが推奨された。https://www.expo2025.or.jp/entranceguide/(最終確認日:2025年10月31日)
*8 大阪・関西万博「お知らせ:2025年8月13日から14日にかけて発生した大阪メトロ運行支障に伴う対応について」https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250818-03/(最終確認日:2025年10月31日)
*9 Osaka Metro「2025年8月13日に発生した中央線の運行トラブルについて」https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20250908_0813r4_unkoutrouble.php(最終確認日:2025年10月31日)
*10 大阪・関西万博「キャッシュレス決済」https://www.expo2025.or.jp/cashless/(最終確認日:2025年10月31日)
*11 大阪・関西万博「Guidelines for Cashless Payment and EXPO 2025 Digital Wallet」(英語)https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/GL9-3-2-Guidelines-for-Cashless-Payment-and-EXPO-2025-Digital-Wallet-EN-Nov.2023.pdf(最終確認日:2025年10月31日)
*12 大阪・関西万博「会場までのアクセス方法」https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/access/(最終確認日:2025年10月31日)
*13 大阪・関西万博「基本計画」https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/masterplan/expo2025_masterplan.pdf(最終確認日:2025年11月4日)
*14 イタリア館では「最大6時間待ち」が報じられた。https://president.jp/articles/-/97925(最終確認日:2025年10月31日)
*15 X(旧Twitter)ユーザー「つじさん」(@t_tsuji)による非公式マップが代表例である。公式マップの情報不足を補うため、予約情報や入場方法などを適宜反映させたマップをコンビニ(ネットプリント)で印刷可能な形式で配布し、累計100万枚以上印刷されたと報じられた。この活動は多くのメディアで取り上げられ、市民参加による情報空間補完の象徴的な事例となった。
ITmedia NEWS「大阪万博「つじ」さんの非公式マップ、100万枚突破」https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2510/08/news078.html(最終確認日:2025年11月4日)
2025年11月発行

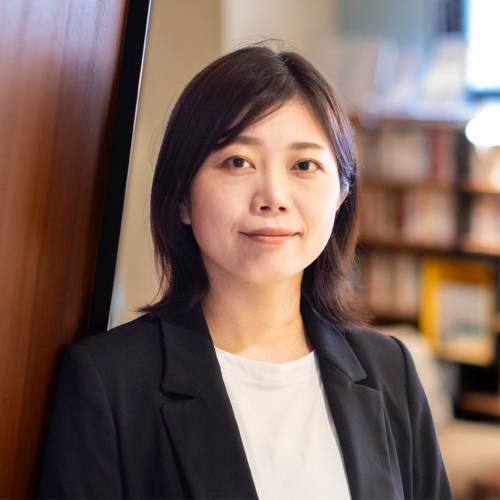

_s.jpg)
