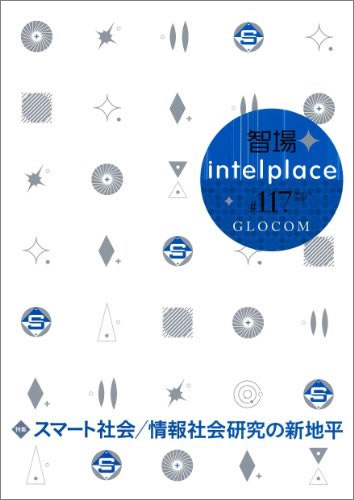◆登壇者:
塚田有那(一般社団法人Whole Universe代表理事/編集者/キュレーター/HITE-Mediaメディアリーダー)
髙橋ミレイ(合同会社CuePoint代表/編集者/リサーチャー/HITE-Mediaメンバー)
庄司昌彦(GLOCOM主幹研究員/武蔵大学社会学部教授/HITE-Media研究代表者)
◆日時:2022年3月29日(火)17:00~18:30
概要
人工知能学会「AI ELSI賞 Perspective部門」を受賞した書籍『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』を取り上げ、編集に携わった塚田氏、高橋氏と共に「死」を切り口にテクノロジーやAI、倫理などの多面的な課題を考察した。講演では、書籍の内容のみならず、書籍発行の契機となったJST/RISTEXのHITE-Mediaプロジェクトや、書籍と連動して開催された「END展」について紹介された。パネルディスカッションでは書籍や展覧会で提起された、死と先端的な技術、社会制度とのせめぎ合いや課題について参加者の質問を交えて議論を深めた。
講演「『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』から考えるAIと倫理」(塚田有那氏・高橋ミレイ氏)
HITE-Mediaとは
塚田:HITE-Mediaとは、科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)の「人と情報のエコシステム(HITE)」研究領域採択プロジェクトの一つ。AIやロボットなどの情報技術が生活の隅々に浸透するなか、人々の暮らしや社会はどう変化するのか。HITEは人や社会への理解を深めながら、どんな問題が起きるかを考え、人間を中心とした視点で新たな技術や制度を設計していく研究領域だ。「HITE-Media」は、異分野の人々を交えて活発な議論の場を創出するプロジェクトで、ここで生まれた様々な「問い」を人々に届け、未来への想像力がふくらむメディア・コンテンツを制作し、情報技術と人々の新たな関係を一人ひとりが考えていくプラットフォームを構築している。(http://hite-media.jp/)
私は冊子やウェブサイトの作成、アウトリーチないしディレクションを担当している。庄司氏を研究代表にメディアチームの形として作られたのが、このHITE-Mediaだが、我々は最初の段階からマンガに着目したいと考えた。AIやロボティクスが進展している未来のイメージはSFやマンガ、アニメが描いてきた世界にインスパイアされていることが多い。そこで、マンガとAIなどの未来思想をクロスさせていこうということになり、研究プロジェクトとして編集者やマンガ製作者など、多様な方々とチームを組むことになった。
最初の年度に「マンガミライハッカソン」を開催して、マンガ家と研究者、編集者がタッグを組み、これからのAI社会がどうなるかを想像して短編マンガを製作するプロジェクトを行った。そこで大賞を取ったチームは今でも活躍していて、我々HITE-Mediaのサイトで新作を発表したり、台湾でも発表したりするなど、いろいろな発展があった。その後、誰にとっても自分事として考えられるテーマは何かと考えて、ふと、綾小路きみまろ氏の「人間の致死率は100%です」という言葉を思い出した。綾小路氏が60、70代から90代ぐらいまでの方を前にこのギャグを言うと会場が爆笑に包まれるというのをテレビで見て、その感じの死生観はいいなと思っていた。どれだけ延命をしたとしても、人間であれば誰にでも死はやってくる。そこから死とこれからの社会、テクノロジーを考えていけばどうかという話がチーム内で発展し、この本を作るきっかけになった。この本を作る前にはAI、ロボット、民俗学の方にも入っていただいて未来の死をテーマに語るトークショーを開催した。これを基にできたのがこの『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』という1冊だ。多様な方々の寄稿やインタビュー、対談という構成になっている。
塚田有那氏
「死後労働」とは
塚田:本の第3章で取り上げたのが「死後労働」というテーマだ。AIが故人を再現することが技術的に可能になっている時代で何ができるのか、人工知能研究者の栗原聡先生とクリエイティブチームに話を伺った。死後労働に明確な定義は全くないが、例として、話題になったAI美空ひばりや手塚治虫の新作を作るプロジェクト(TEZUKA2020)がある。AI美空ひばりは2019年紅白歌合戦で登場したことで賛否両論物議を醸した。TEZUKA2020では手塚治虫が新作を作ったという言い方をせず、手塚治虫という偉大な漫画家の知恵をどう生かすかというプロジェクトとなっている。他にも話題になった例として、韓国で2020年に放映されたドキュメンタリー番組「Meeting You」という番組がある。著名な方々がAIで再現されることは想像に難くないが、これは一般の方を再現することも可能になるという例だ。当時の写真や身振り、しゃべり方を家族からヒアリングして、幼くして病気で亡くなった娘をVR上のアバターとして正確に再現し、母親がVR空間で出会うプロセスを紹介したドキュメンタリーだ。やはりこのように出会える可能性があることに、コメント欄を見ても賛否両論になっている。番組制作のプロセスにはカウンセラーがついており、この母親や家族からヒアリングをしていくこと自体がグリーフケアにつながったという文脈もある。だが、一方でこの話だけを聞くと死者の冒涜ではないかとか、こういうことができてしまうことが受け入れがたいという意見もあって物議を醸していた。これが是か非かということは我々も記していないが、技術的にこのようなことが起きてしまうという社会を考えていかなければいけないのではないかという意味で特徴的な話だと思う。
続いて、アメリカで2020年に発表されたYouTubeの動画のプロジェクトで、「UnfinishedVotes.com」というものがある。2017年にアメリカ・フロリダ州の高校で起きた銃乱射事件の被害者の一人であるホアキンさんという少年を、両親の協力を得て再現させるというプロジェクトだ。これが発表されたのが2020年10月で、ちょうどアメリカ大統領選挙の前だった。これで「誰かが変えてくれるのを待つのはうんざりだ」と訴えているのだが、このあとに「もう僕は銃社会には反対だ、だから選挙に行こう」と呼び掛ける、政治キャンペーンとして使われたプロジェクトでもある。確かに彼も銃社会に反対をしたかもしれないが、本当にそれが彼の遺志だったのかは言い難い。両親、遺族が良いと言ったとしても政治的な発言をさせていいのかという面で物議を醸すプロジェクトだったといえる。髙橋:こういう技術が実用可能になると、いろいろな形で亡くなった人を復活させる試みが事例として増えてくる。栗原先生はインタビューの中でもTEZUKA2020とAI美空ひばりを比較して、どう伝えるかが非常に重要であると仰っていた。半ば炎上という形になったAI美空ひばりは「故人の復活」というイメージを前面に押し出してしまった。一方でTEZUKA2020ではそれを見ての教訓もあり、メディア露出の際には「手塚治虫が復活する」という言い方はできるだけしないようにしたと言っていた。
塚田:AI美空ひばりは2019年末のことで、我々が取材したのが1年半後ぐらいだったので、いろいろなインタビューでこの話題が出た。よく言われたのが、歌うだけだったらまだしも「久しぶり」と語らせたところに違和感があったという話だった。これに関して、先ほどの韓国のドキュメンタリーの話を高校生にしたことを思い出す。END展直前のプレ企画として角川ドワンゴ学園(通称N高)の生徒向けに未来の死を考えるワークショップを行ったのだが、その時に、アバターで再現することが正確になればなるほど、どこかでずれを感じるはずだ、何か違うと思った瞬間により悲しみが増してしまいそうだと言った生徒がいて、それは鋭いと思った。よくロボット問題で「不気味の谷」と言われるが、死者のアバターにおける不気味の谷は今まで議論された、「人間に似すぎていて気持ちが悪い」という点とは違うところに発生しそうだ。
髙橋:技術によって生と死の境界が揺らぐと似た問題が出てきやすくなると思う。AIではなくバイオテクノロジーの話題になるが、死んでしまった飼い猫、飼い犬のクローンを作るというサービスが1000万円ぐらいでできると話題になっていたことがある。私も猫を飼っているが、この先、その猫が死んでしまったあとにクローンを作ったとして、それを同じ猫だと思って一緒に暮らせるのだろうかと疑問に思う。些細な違いが見えたことでむしろ余計に死んでしまった猫の不在が強調されて、より深い悲しみを覚えてしまうのではないかと思う。
高橋ミレイ氏
塚田:そういうこともできる中で、別の記事で紹介したのがクリエイティブスタジオの富永勇亮氏や川村真司氏が行っているD.E.A.D.プロジェクト(https://dead.work/)だ。今後、家族が生前に確認することもなく個人データを復活させることが、技術的に可能になるという時代になる。そこで、個人データを復活させられることを許可するかどうかを生前に表明することが必要とされるのではないかと考えてアンケートを取ったり、法的根拠はないのだが、自分の意思を表明するカードを作ってみたりすることを行っている。
髙橋:こうしたことは今後ますます重要になると思われる。一方で先ほど話題に出た「UnfinishedVotes.com」は批判も多いが、これは遺族が許可を出しさえすれば個人の意志や人格を無視することにもなりかねないという問題提起もはらんでいる。だからこそ、D.E.A.D.のように、事前に本人が「自分の個人データをこういうことになら使ってもいい」という取り決めができるのであれば、関係者や社会全体としても納得がしやすいのではないか。
塚田:このプロジェクトの二人でも意見が割れていて、富永氏は復活させられたくない派で、データも全部取っておくというタイプだが、川村氏は家族に何らかの自分の創作物が入っていくのであれば、むしろ積極的に使って欲しいということだった。また、情報社会学の折田明子先生は基本的にSNSのデータは消してほしいという人は多いが、家族や友人の関係性が分かるLINEや写真は遺族のために残してもいいのではないかと話している。データもいろいろなものがあるので、関わる人で複雑化すると思う。
第4章では死者のアイデンティティと権利というテーマで、死後のデータはどういう法制度で守られるのかなどを弁護士の水野祐先生にお聞きしている。死後の個人情報の保護に関しては、日本を含むほとんどの国できちんとした規律はまだ存在していない。生きている人のプライバシーに関するものはあっても、死後に関してはまだ明確に規定されていないのが現状だ。ただ、生前の顔写真をパブリシティで使うことに関して、アメリカ・カリフォルニア州やニューヨーク州はほかの州に先駆けて「死者のパブリシティ権」を権利として認め始めている。カリフォルニア州はハリウッドがあり、ハリウッドセレブたちの肖像などはメディア上で露出することが多いので、前からこの議論はあったらしい。死後のデータに関する権利がなければ、実際に誰かが勝手にマイケル・ジャクソンの生前のデータからVR空間で再現ライブをすることも可能だ。それに対して禁止するという話になる。髙橋:実際、現時点で、死後労働で最も稼いでいる人物はマイケル・ジャクソンだと言われている。
塚田:美空ひばりを誰かが勝手に作ることもできるし、例えば公演をするまでいかなくても、YouTubeでアップしていたら結構その再生数が上がることも考えられる。
個人データ利用の考え方
庄司:私は、基本的にデータは多いほどいい、世の中で使えるデータが増えるといいと思ってオープンデータのようなプロジェクトをたくさんやってきた。さらに、データをできるだけ使おうという考え方でこれまでいろいろとやってきた。書籍ではパーソナルデータ活用の方向性を整理して図表を書いたのだが、私的利用と公的利用、それから、生存中の利用と死後の利用という4象限が作れる。①は生きている間に自分のデータをコントロールしたいということで、個人情報の活用の話だ。②は死後、自分のデータをどうするかということで遺書、遺言というものになる。生きている間に公的に使ってもらおうというのは、コロナ関係とかプライベートな健康データをどう使ってもらおうかという話になってくる(③)。さらに、死んだ後に私のデータをどう使ってもらおうかということは、社会貢献としてのデータ活用という話になる(④)。いずれもそれに当てはまるという事例が出てきていて、さあどうしようかというのがこの章になる。今回これを書きながら、各自が豊かな人生を選んでいくという観点からは、「データは増えるほどよい」「データがあるならできるだけ使うべき」という根本を疑う必要があるのではないかと感じた。
庄司昌彦氏
塚田:④の社会貢献としての死後のデータ活用はあまり馴染みがないと思う。
庄司:たとえばソーシャルメディアには、コロナ禍の2年間に私たちが何を書いて、どんな生活をしていたかという記録が残っており、またスマートウォッチなどでは四六時中、私たちの健康データを取ることも行われている。こういった世界中のデータを公的に使えれば、莫大な価値のある資源となっていろいろな研究はできると思う。ただ、データがあるからそういう発想が出てくるが、それはどうなのかということだ。
塚田:例えばアイスランドでも国民全員の遺伝子情報を取るといった遺伝子バンクのプロジェクトがあり、国内の医療機関や研究機関が実際にそれを使って成果を上げている。
庄司:アイスランドは外との行き来が非常に少ないところなので遺伝子的に安定的という背景もある。
塚田:特にDNAは一個人が自分の情報を開示してよいと言っても親族にも関係してしまう問題になるため、そこが議論の種になると思う。だが、逆に個人情報のように自分で保護をする①番の考え方から④番までいくと、いかに個人から離した状態でデータとして提供できるかみたいなところにも関わってくるのではないか。
庄司:データの観点でいえばそういう話になるが、皆の役に立つからといって個人が全体に奉仕しなければいけない社会で良いのか。社会科学者としては、国民だったら国のために働け、といったことは余計なお世話だと思う。自分の身の回りの範囲で貢献したいというのは自然の感覚かもしれない。だが、全員が国のデータベースに取られるという社会は、技術的にはできるが、社会科学や個人の人生のあり方を考えるとどうかと思う。
髙橋:選択肢があればいいと思うが、ほとんどのデータを吸い上げるのは違和感があるし、自分やそれを取り巻く人たちのプライバシー保護の面でも心配だ。
塚田:結局公的機関がどういう選択肢を出すか以上にGoogle、Apple、Facebookなど、いわゆるテックジャイアント企業に勝手にデータを吸われているという状況が今起きているわけで、そことの矛盾も考えてしまう。
死にまつわる意思決定
塚田:第5章では医療現場、生死に関わる現場でどんな選択が起きるのかという話をした。
髙橋:小門穂先生は生命倫理がご専門で、リプロダクティブライツ、つまり妊娠出産に関わる権利や法制度、特にフランスの法制度について研究されている方だ。フランスでは例えば性的少数者の方が暮らすことのできる環境が整備されていて、多様な家族の在り方が認められるようになっている。それでもやはり社会の中で偏見が残ってしまうと思うが、法制度ができてパブリックな場所で権利が認められるということは非常に大事なことではないかと思う。
塚田:今、出生前診断とか精子バンクが社会サービスのひとつにもなり始めているが、そもそも生き方を選ぶということが社会通念的に浸透していくと、死もコントロール可能になるのではないかという話もあった。
髙橋:それについては、例えば安楽死が合法的になることで、家族に迷惑をかけるから死ななければならないという同調圧力も生じる可能性があるため、より丁寧な議論や制度設計が必要だと考える。
塚田:HITEプロジェクトで医療現場と意思決定にAIがどうかかわるかという研究をされていた尾藤誠司先生の話で面白かったことがある。例えば、インフォームドコンセントといって、延命治療をするかしないかを、医者側から伝えられた情報に対し、患者側が納得をした上でサインをするという規定がある。ただ、臨床の現場に直面している現場からは、それはファンタジーだというのだ。おばあちゃんが生きるか死ぬか、延命治療するかしないかということは、おばあちゃんがいるにもかかわらず、病室の隣で家族と医者の間で決まっているということも多々ある。現場のリアルな話として、安楽死するかしないか、たとえば「今から呼吸器を抜いてください」などと本人が願ったとしても、そう簡単に本人の意思が通ることはないということだった。もう一方で尾藤先生は、人間の意思は今日も明日も変わりうるという「変容する自己」という言葉を使われる。延命するかしないかという重大な決断を考え抜いて今日の私がサインしたとしても、明日の私が納得するか、後悔するかは分からない。そういう状況を踏まえずにイエスと書いたからというだけで物事を進めてしまう問題や、専門家が一方的に情報を伝えることで「はい」としか言えなくなってしまう状況を踏まえたうえで、AIによる診断のようなテクノロジーも浸透している時に、人間の意思はどうなるのかという根本的な部分から問い直す必要があるという話だった。
髙橋:自己の意思が変容することを前提に意思決定をサポートできる態勢を整えるのが大事という話があった。人の意志というものは、例えばお昼にラーメンを食べたいと思って出かけたとしても結局カレーを食べるように、もともと些細なことで変わりやすいものだと思う。まして人の生死に関わる重大な事なら時間の経過と共に大きく揺らぐのは無理もない。
塚田:アドバンスケアプランニングになる。リビングウィルといわれる時の意思とか何をしたかということを日記のように書き留めていくということで自分自身の考えがどう変容したかを一度見直すとか、超高齢化社会を迎える中で意思統一して生死をどう決めるかという話を考えていくことも重要な課題になるのではないか。
END展
塚田:2021年11月3日から14日に、書籍の中身を少し違う形で構築した展覧会を行った。ビルの3フロアを使った会場で、12日間で1000人以上の方にお越しいただいた。死ということを考える機会があまりないので、すごくいい機会だったという好評の声をいただいたり、SNSの反響も大きくて、END展というハッシュタグで死を考える企画が面白かったと言われた。構成として、一人ひとりに死について考えて欲しいという思いがあったので、死にまつわる問いを掲げた。昨年の6月から7月に行ったアンケートの結果をグラフとして紹介し、これに関連する漫画の一コマを合わせ、その3つを1つの組として展開した。
結構面白かったのはアンケートの自由回答の部分だ。誰かの死に関して今でも覚えている印象的な夢や出来事はあるかと聞いてみると、現代の遠野物語といえるぐらいユニークな回答が集まった。「母が亡くなる3日前、突然目を覚まして霊界から招待状とビールが来たと叫んだ」とか「白い蛇が来たと思った」とか、コロナ禍で見舞いができず祖父の死に行く過程に寄り添えなかったので、今も骨を持ち歩いているという話まで、普段、友人知人にもあまり話すことがないのではないかという内容で、いろいろなナラティブが立ち上がった回答集だった。
この展覧会は一人ひとりの声や想像力、または語り得ていない感情や思いを放出する場にしたいと思ったので、アンケートの結果をそのまま展示するという構造にした。他にも死がどう揺れ動いているのかということで、折田明子先生のデータに関する解説を展覧会場で紹介して死後SNSを残してほしいかを聞いている。回答では「消去してほしい」が半分ぐらいになるのだが、死ぬ前に3時間をもらえたら残すのを決めるという話題も出たりして、いろいろな声が出てきた問いのひとつだった。他にも先ほど紹介したVR上で償還するという動画を見せた後に、もし死者に会うことができるとしたら会いたいかとか、機械の誤作動で人が亡くなったら誰の責任になるのかといったことも聞いたりした。最後のステージでは魂の問題について聞いている。今、自然の一部になるという感覚が、需要としては増えているのではないかと思う。今までのお墓に入るイメージではなく、海に撒いてほしいとか、既存の家システムから解放された形で死を迎えたり、死後は解放されていきたいという意見もある。そこで死後、自然の一部になりたいかという問いを書いたり、葬儀空間と居住空間を分けるべきかなどと聞いた。展覧会の入口でアンケートとポストイットをお渡しし、2100年の死はどうなっていると思うかという問いを投げかけた。そうすると想像以上にいろいろな声が集まって、最後は貼り切れないくらいの状態になった。最初に未来の死と言われても答えられなかったと思うのだが、展覧会を見たことによって想像力が喚起されるような状態になって、ユニークな答えが集まった。これは誰が書いても絶対に正解がない。そういうところも良かったと思う。パネルディスカッション
――人文科学と科学技術の研究者をつなぐためには、両方の世界の言語や世界観への理解が必要。塚田さんはどのようなバックグラウンドか。どうすればそのような人材が育つのか。
塚田:私自身はそもそも文系で、今でも基本とする活動はアートやデザインに関わるものが多い。だが、12、3年前、学生時代にたまたま生物学に進んだ研究者と出会ったのが起点だった。サイエンスの世界を理解しようとする前に、面白いと思ったことが最初の入口としては良かったと思う。日本の学校教育が理系文系と分けているだけで、数Ⅲを諦めたからといって理系に行けないわけではない。日本が定めた理系文系の枠からいかに開放するかが最初だと思う。
髙橋:好奇心を起点に世界を広げることはとても大事だ。私は10代から20代の途中まで環境活動に携わっていた。環境問題は科学技術だけでは解決できないため、人文社会学的な目線からも分析をしてアプローチする必要もある。関心があれば、学際領域でないとアプローチできないような領域に思い切って飛び込んでみるのも選択肢だと思う。
――死がどう変わるか結論を聞きたい。
塚田:結論は永遠に出ないのではないかというのが結論になると思う。肉体的に人は死ぬので、どう受け止められるかというのは千差万別だろう。方向性は2軸あると思っている。ひとつはデジタル化だ。死後、死者のアバターが作られることがざらにあるだろうし、もしかしたら死体をそのまま残すようなことや、アンチエイジングみたいなことももっと発展するかもしれない。いずれにせよテクノロジーによって何らかの情報を残す方向を目指すというデジタル化の方法だ。もう一方で展覧会でも紹介したように、残り続ける時代に対して、もう自然に帰ろう、墓もいらないという欲求やニーズも増えてくる気がする。代々家で墓を守るというシステムはどうしても今の時代と合っていないと思う。最近アメリカでもたい肥葬といって、自分の肉体を養分に早く返らせる方法が開発されていて、とてもニーズがあると聞く。デジタル派、自然派という大枠に分かれていくのではないかと思っている。髙橋:実は過去100年でも大分変わっているのではないかと思う。最近は家のお墓に入るのではなく散骨をしてほしいとか、非常に個人の価値観や死生観に寄せた弔い方を希望する人が増えてきている。これはコミュニティの持つ慣習よりも個の意志を優先する方向に社会のあり方が変化したことの表われではないだろうか。おそらく100年前だったら仮に希望があったとしても、なかなか周囲が認めなかったのではないかと思うので、死にどう対峙するかということは大分変わってきているのではないかと思う。従ってこの先、2100年になったときにどう変わるかというのは、おそらく、その時の社会が一般的に個人の意思やアイデンティティをどう捉えるか次第ではないかと思う。具体的にこう変わるという答えを出すことは今の時点ではできないが、より個人主義は加速していく気がするので、例えば堆肥葬などが普及するなどより多様化していくかもしれない。
庄司:2100年ぐらいまでをスパンに置いてしまうと、本当に生物学的な死も変わる可能性も無きにしも非ず、だと思う。今日の話にあったように、自分の意思や表現したものを残したり活用したりしやすくなっているので、肉体は死んでも自分の意思を何らかの形で活かすことができるようになるのが一つのポイントではないか。そして、弔いに周りの人の側がどう関わるか。今まではたとえば法事のように年単位で思い出す機会があるという弔い方をしてきたが、ソーシャルメディアで日常的にコミュニケーションができたり、VRの中で毎日会うことも可能になるなかで、死そのものは変わるかもしれないし、死の受け止め方にだいぶ幅が出てくるのではないかと思う。そのときに自分がどうするか。
髙橋:最近見た中国のテックニュースで、亡くなった人の個人データやSNS履歴といったデータを集めて、バーチャルヒューマンをタブレット上に再現するサービスが紹介されていた。自分が仕事で悩んだときに、亡くなったおばあちゃんに話しかけると会話して励ましてくれるというサービスだ。RE-ENDで、未来でこういうことが起きるのではないかと述べていることが既に起こりつつある。
庄司:RE-ENDの漫画作品に、本人が出てきて自分の葬式を主宰するというのがあった。
髙橋:死後労働にも、本人の意思(遺志)に基づくものと、基づかないもの(周囲の人々が利用する)がある。後者は問題になることが多い。
塚田:周囲の人が勝手に利用して、フェイクニュースのようにいくらでも量産できてしまう状況だと思うので、規制だけでそれを取り締まれるのかというと悩ましい。結論は出ないのだが、起き得るということを今から考えておくしかないと思う。
庄司:私は本人の意思に基づくものでも問題になるケースがある気がする。例えば、今、陰謀論にとりつかれたまま亡くなる方がいて、死後もそうしたことをネット上に吐き続けるようなことが続くと困る。これはいかに生きるか死ぬかということを考えるきっかけになると思う。
――死後、データを元に復活するとして、それは一意に定まるのだろうか。異なる個体として復活させることも可能だと思うし、複数復活したら、その後の経験がますます別の個体に変化していくような気がする。生前の継続で一人だけが復活するということがないのでは。
塚田:現代のメディア論ともつながる話だと思う。私がZoomで話していることもSNSに投稿することもメディアを経由しているといえる。というのは、メディアのプラットフォームを経由して最適化して出ているわけで、Twitterで100字でつぶやいたことと、インスタで写真を撮ったこととZoomの講演会で話していることと、分人的というか違うわけだ。インターネットや何らかのメディア、プラットフォームを経由している時点で個のアイデンティティというのは一個の固有の普遍的なものであり、そもそも存在しないという考えに基づかないと存在しない。まずそれを考えるのが基盤になると思う。そもそも死ぬ前からそうだったということに立ち戻れるテーマでもあると思うので、死後というテーマを設定した方が現状を因数分解しやすくなると思っている。
髙橋:そもそも人間自体が多面体ということでは。
庄司:尾藤先生の話のように、生きている本人でも昨日の意思決定と今日の意思決定が同じとは限らない。
――AIの発展による死の受け止め方の違いには、国情の違いも出ているのか。例えばロシアではレーニン廟に高度なエンバーミング技術で保たれたレーニンの遺体があると聞く。そのような国ではAIにより偉大な指導者を残すというのは自然な選択になる気もするが。
塚田:絶対にあると思う。イーロン・マスクしかり、IT企業のCEOが先行的にやっていくと思うが、国の地域文化差もあるだろうし、権力を持った人が何を望むかによって軸が変わってくるのではないかと思う。
庄司:国情の違いはどうか。日本なら日本なりの考え方というのがあると思う。
塚田:ロシアの話もあるが、今も戦時下において何かを残そうと希求する世論が集まると、平時の状態とは全く変わってくると思う。国情もそうだが時代によって本当に変わる。去年なら国によって違うと言えたが、今は簡単に言えない。違いは出てくると思う。
庄司:HITE-Mediaの1000人アンケートでは、「歴史上の偉人の人格や知性をAIで復活させて国を統治できるとしたら、賛成ですか」という問いに対して、45%が反対、何とも言えないが27%で、逆に賛成に近い人は合計11%しかいなかった。日本だからそうなのかもしれないし、指導者次第で国が左右されるというのを見る前だったからかもしれない。
髙橋:同じ質問を他の国でもやってみたい。
塚田:歴史上、偉人がいる国かどうかでも変わりそうだ。
――こういったプロジェクトにマンガ家の方に関わってもらうときに、技術的な正しさにこだわると面白くなくなり、自由に想像力を働かせていただくと非現実的な内容になる恐れがあるのではないか。編集者として、あるいはプロジェクトとして工夫された点はあるか。
塚田:何を目的とするかで違ってくる。そもそも技術の正しさがどうかというより、死はどうなるかというのを問いかけたものになる。しりあがり寿さんやうめさんには、プロジェクトに早い段階から参加してもらって、対談してインスピレーションを基に書いてくださいと言ってあった。編集者として工夫する点と言えば、ただ書いてくださいと依頼するのではなく、書く前に対話をするとか、資料を一方的に渡すのではなくそれを踏まえてどう書いていただきたいかを話すのが重要だと思う。
庄司:五十嵐大介さんはプロジェクトにぴったりな絵を描いてくださったが、基本的に、遠隔でやりとりをしていたのか。
塚田:実は2、3回Zoomでお話した程度だ。資料はお渡ししていて読み込むのは大変だったと思うが、かいつまんで説明するぐらいだった。その辺りは作家さんの力だろう。こちらがある程度の話をした段階で「ちょっとラフを書いてみます、それを見てください」と言ったかと思ったらすごいのが出来上がってきたという感じだった。依頼するにあたって、事前にどういうタイプの作家さんなのかを把握しておくことが重要だし、漫画ならなんでもいいわけではないので、この人だったらこう描いてくれるだろうなというイメージを最初に持った上で、熱意プラス愛情みたいなものを持ち続けられるかどうかが、こうした創作物に関しては重要だと思っている。
庄司:事前に漫画家さんのことを理解しておくということか。
塚田:そのほうがうまくいく場合が多い。私も漫画のプロジェクトは初めてだったが、作家への理解、どういうタイプかということをよく知っておくのが重要だと思う。
庄司:最後に一言ずついただきたい。合わせてお薦めの章があれば伺いたい。
塚田:西洋的な価値観や中南米、アフリカなどいろいろな死生観はあると思うが、東アジアにおける死生観、日本における死生観という部分はやはり違いはあると思っている。RE-END2を作るなら自然観とか、土にかえるという感覚をどう人が持ってきたのかというのは人類学的にも研究されているテーマだと思うので、やってみたい。
この展覧会が好評だったのはコロナがあったことも一因だと思っている。この2年間、毎日の死者数を耳にしながら未だに実感がわかないという、とても不思議な時間を過ごしてきたと思う。常に死というものを目にする機会があるという状況のなかで、展覧会でいろいろな声が集まったというつながりは強かったのではないか。もしオリパラで日本が浮かれている時期だったら全然響かなかったのではないか。5月末から6月まで開催されるEND展では角度を変えて、社会の中で起きる死は何かということを考える中身にしていきたい。展覧会を開催するにあたって、ウクライナをどう考えるかということに正直答えは出せないが、念頭に置いて考えたいとは思っている。髙橋:ロシアのウクライナ侵攻に関して、自分で何か影響があったかというと実はそんなにない。ただ、日頃AIに関する情報を追っている立場から、近年ロボット技術やAIがどう軍事転用されているかをリサーチしたところ衝撃を受けた。その進化の系譜からも軍事とAIは切っても切り離せない関係だと頭では分かっていたのだが、事例を調べていくと、例えば、自立型“致死”兵器システムと総称するものがある。また、ヨーロッパは軍事AIを議論する委員会で軍事AIとELSIに関わるガイドラインについて議論をしており、改めてAIの社会実装は非常にシビアな分野だと実感した。
RE-ENDでお薦めのページは「ゲーム世界における<他者>とAI」という寄稿記事で、これはAI時代のアイデンティティにフォーカスした話だ。死生観は詰まるところ個人のアイデンティティをどう捉えるかということの延長上にある問題であり、故に世界をどう捉えるかという問いにも直結する。この記事はオンラインゲームなどで、AIを実装したエージェントと一緒に遊ぶゲームを前提としているが、これはSNSなどオンラインコミュニティでのコミュニケーションにも適用可能な話だと思う。例えばTwitter上のボットと人間の区別がだんだんつきにくくなっているし、チャットボットがさらに進化し、非常にフォトリアルなアバターを持つデジタルヒューマンが作られ、ディープフェイクの精度も上がり、場合によってはそれらが世論の誘導やプロパガンダにも活用できてしまう。そのような世界で自身はどうアイデンティティを形作り守るのかを考えながら読んで考えていただくと良いのではないかと思う。庄司:私もウクライナに関しては、本当に不条理に死がやってきていると感じている。コロナもそうだったのだが、普通に生きている人たちが何で?というような理由で死んでしまうという状況だ。その怖さはもしかすると、昔よりも増しているのではないか。戦争が滅多になく、病気で多くの人が死ぬということが克服されてきて、人は長生きする。そんな中で若くして死んでしまうことが確率的に昔よりも不幸な出来事、運が悪いという意味になってしまう。なかなか死なないからこそ、死が怖いということもあるのかなと考えた。
お薦めしたいのは、しりあがり寿さんと畑中章宏さんの対談で、これはHITE-Mediaサイトに動画も出ている。死なない時代だからこそ、死についてもう少し我々は生前から考えなければいけないのではないかという話をしている。デジタル庁や子ども庁もできるようだから、死者庁も作ったらいいのではないかと話しているのだが、この2人の話はとても深いと思う。
執筆:井上絵理(国際大学GLOCOM客員研究員)