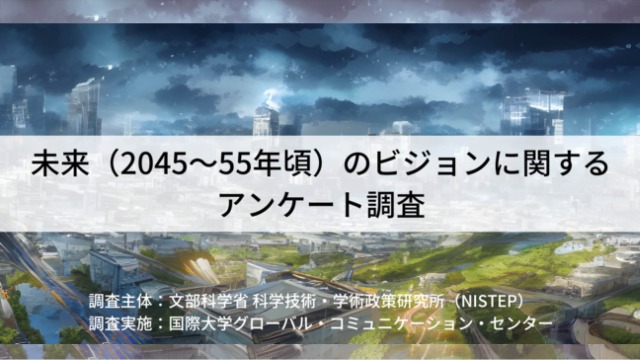講演資料PDF
※イベント開催レポートは、後日公開予定です。
開催概要
日時 :2025年3月14日(金) 11:00~12:00(受付10:30~)
会場 :ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1F「ギャラクシー」
(東京都港区赤坂1-12-33 地下1階)
https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/
※対面参加のみでの実施です。アーカイブ動画等の公開予定はございません。
言語 :日本語および英語(同時通訳付き)
参加費:無料
定員 :100名(先着順)
主催 :国際大学GLOCOM
協賛 :日本マイクロソフト株式会社、Business Software AllianceAIのガバナンスをめぐる制度形成やその方向性についての議論は世界中で活発に続いており、開発だけでなくAI活用サービスの設計やAI利用にも影響するものとなっています。
AIガバナンスを通じて追及するべき価値や目的としては、AIの安全性や信頼性の確保、国際競争力強化、国際協調や安全保障、といったものが従来より存在してきましたが、そのバランスや組み合わせの最適解は模索中です。
EUでは、人権や民主主義を重視するAI法の具体化が実践規範(Code of Practice)策定などを通じて進められていますが、競争力が規制によって損なわれる事への懸念を強く持つ人も存在し、一定の影響力を持っています。米国は第二期トランプ政権がAI関連政策を変更し、一部の政府内ガバナンスを緩めつつ、AI開発をめぐる国際的な主導権を強調しています。韓国は従来から国際的リーダーシップと安全性を共に重視して来ましたが、25年1月のAI基本法制定により生成AIを含む一部AIの安全性義務やAIセーフティーインスティテュートに法的位置づけを与えました。日本では、AI戦略会議の中間とりまとめ(案)を通じ、政府の多様な施策を一体的に推進するための司令塔機能の法定化などが打ち出されています。技術面での進展、例えばAGI(汎用人工知能)の実現が迫っているという説が増えたことや、DeepSeekが見せる開発アプローチの可能性なども、安全性や競争力をめぐる議論に影響を与えています。
本シンポジウムでは内外の専門家を迎え、国際動向の捉え方、日本のAIガバナンスの追求するべき価値やその実現方法、日本の国際的な役割について探ります。AI技術の開発や普及の支援・規制に関心を持つ幅広い皆様のご参加をお待ちしています。
参加お申込方法
下記ページ(Peatix)よりお申込みください。
https://peatix.com/event/4314050/view※お申込締切:2025年3月13日(木)12:00→定員に達したため締め切りました(3/13 事務局)※参加登録済みの方には、開催前日までに当日のご案内メールをお送りいたします。
※お申込み時に頂いた情報は、イベントの円滑な運営のために登壇者など実施に関わる方々と共有することがございます。同意の上お申込みください。プログラム
開会挨拶
講演①(15分)
- 渡邊 昇治(内閣官房 内閣審議官)
講演②(15分)
- Marcus Bartley Johns(マイクロソフト 公共政策担当アジア地域シニアディレクター)
パネルディスカッション(25分)
- 渡邊 昇治(内閣官房 内閣審議官)
- Marcus Bartley Johns(マイクロソフト 公共政策担当アジア地域シニアディレクター)
- Jared Ragland(Business Software Alliance アジア太平洋 (APAC) 政策担当シニアディレクター)
- 村上 明子(AIセーフティ・インスティテュート 所長/損害保険ジャパン株式会社 執行役員CDaO)
- 中尾 悠里(富士通株式会社人工知能研究所 シニアリサーチマネージャー)
閉会挨拶※一部登壇者が変更になりました(2025/3/4付)
※一部変更になる可能性があります
※登壇者敬称略・順不同
※同時通訳あり登壇者プロフィール※登壇順、敬称略
渡邊 昇治
内閣官房 内閣審議官
1990年東京大学大学院修士課程修了(工学修士)、通商産業省入省。新エネルギー対策課長、産業技術環境局研究開発課長、商務情報政策局情報政策課長、総務課長、大臣官房審議官(産業技術環境局担当)等を経て、2020年内閣官房審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室)。2022年内閣府科学技術・イノベーション推進事務局事務局長補([併] グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室、AI戦略チーム)、2023年同事務局統括官。2024年7月現職に就任。Marcus Bartley Johns
マイクロソフト 公共政策担当アジア地域シニアディレクター
プライバシーやデータ保護、人工知能の責任ある活用、サイバーセキュリティ、スキルと仕事の未来といった、アジア地域全体におけるテクノロジーと社会の幅広い課題について、信頼性が高く包括的なデジタル変革のための公共政策と規制を推進している。マイクロソフト入社以前は、シンガポールとジュネーブを拠点に、世界銀行で政府のデジタル経済と貿易のプロジェクトに従事し、東南アジアのデジタル経済、世界貿易と貧困といった主力報告書を作成したチームの共同リーダーを務めた。オーストラリアの外交官としてキャリアをスタート、ジュネーブでは世界貿易機関と国連に勤務、バンコクでは地域経済協力プログラムに取り組んだ実績がある。Jared Ragland(ジャレッド・ラグランド)
Business Software Alliance アジア太平洋 (APAC) 政策担当シニアディレクター
Business Software Alliance(ビジネス・ソフトウェア・アライアンス、BSA)のアジア太平洋地域(APAC)政策担当シニアディレクター。BSAの会員企業と共に、日本、中国、インド、インドネシア、韓国、ベトナムなど、アジア太平洋地域の重要なマーケットにおける市場開拓、イノベーションの促進、デジタル貿易の推進を目的としたBSAの国際戦略を策定。BSA シンガポール事務所勤務。
前職では米国特許商標庁(USPTO)の知的財産権を専門とする領事館員として駐上海 米国総領事館に勤務。それ以前は米国通商代表部(USTR)で知的財産・イノベーション部局勤務。2005年9月~2007年11月の間、米国国務省経済政策局 東アジア・太平洋支局で科学政策の参与を務めた。
2004 年にワシントン大学で分子細胞生物学の博士号を取得。アリゾナ大学で生化学の理学士、東アジア史と人類学の複数専攻で学士号取得。村上 明子
AIセーフティ・インスティテュート 所長/損害保険ジャパン株式会社 執行役員CDaO
1999年日本アイ・ビー・エム(株)入社、同社東京基礎研究所において研究に従事。2021年に損害保険ジャパン株式会社に転職、損害保険のデジタル・データの利活用の推進をしている。2022年4月より同社執行役員CDO(チーフデジタルオフィサー)としてDXを牽引、2024年よりCDaO(チーフデータオフィサー)となり、データ戦略を担う。2024年2月、AI Safety Instituteの設立とともに、初代所長となる。損害保険ジャパンとは兼任となる。中尾 悠里
富士通株式会社人工知能研究所 シニアリサーチマネージャー
2015年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程修了。同年株式会社富士通研究所入社。富士通株式会社人工知能研究所シニアリサーチマネージャー。青山学院大学大学院非常勤講師。内閣府AI制度研究会構成員。経済産業省AI事業者ガイドライン検討会委員。専門は科学技術社会論、責任ある研究・イノベーション、ヒューマンコンピュータインタラクション。著書に『AIと人間のジレンマ:ヒトと社会を考えるAI時代の技術論』(千倉書房)。お問い合わせ
イベント事務局(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター内)
〒106-0032 東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル2階
担 当:安藤
メール:info_pf[at]glocom.ac.jp ← [at] を小文字の @ に置き換えて送信してください。
電 話:03-5411-6677