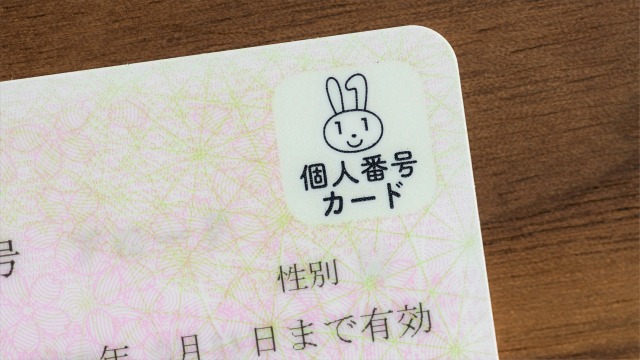講師: 加藤悠介(総務省 情報流通行政局 情報通信経済室長)
コメンテータ:庄司昌彦(GLOCOM主幹研究員/武蔵大学 社会学部 教授/『情報通信白書』アドバイザリーボード)
日時:2025年9月19日(金)18:00~19:30
概要
令和7年版情報通信白書は、特集テーマ「広がりゆく『社会基盤』としてのデジタル」として、我が国および海外との比較を通じてデジタル領域の拡大や、AIの爆発的進展の動向等を概観している。講演では我が国におけるAI普及の課題やデジタル赤字、トラヒック、研究開発といった今後のデジタル領域拡大に伴う課題が示された。質疑応答では、これらの課題への対策に向けた質問が寄せられ、国や企業の対応だけでなく個々人の積極的なAI利活用やリテラシー強化の必要性などが指摘された。
講演1「令和7年版情報通信白書 ~広がりゆく「社会基盤」としてのデジタル~」(加藤悠介氏)
社会基盤的機能を発揮するデジタル領域の拡大
情報通信白書は正式名称「情報通信に関する現状報告」というもので1973年に初めて発行され、今年で53回目となる。構成はⅠ部とⅡ部に分かれていて、Ⅰ部は特集になっている。Ⅱ部は情報通信分野の現状と課題として、第1章はICT市場の動向として経済分析を行い、第2章は総務省におけるICT政策の取組状況を紹介している。
今日はⅠ部の特集をメインに話をさせていただく。今年の特集では、デジタル領域の拡大ということで、SNSやクラウド、AIの爆発的な進展を概観している。ここ10年を振り返るとデジタルが我々の社会や生活に浸透し、インフラのような形で広まっている。一方、それに伴い独特の課題も生じているので、どういった対策を取るべきかを特集テーマとしている。
インターネットの接続端末について時系列で取ったデータを見ると、2024年には74.4%の人がスマホを使ってインターネットにアクセスしている。スマートフォン経由でネット接続している60代の利用者も右肩上がりで増えている。10年間の企業のクラウドサービスの利用率の推移を見ると、2014年、企業の利用率は約4割だったのが倍増しており、約8割の企業がクラウドを利用している。
最も利用しているテキスト系ニュースサービスを聞くと、2024年はいわゆるGoogleやYahooなどの検索エンジンを経由してニュースを見ている人は46.8%であった。また、インターネット経由(非新聞社系)、つまりLINE NEWSなどソーシャルメディアによるニュース配信や、キュレーションサービス(グノシー、スマートニュース、News picksなど)を経由してニュースを見ている人は75%を占めている。次に新聞通信調査会の調査結果を引用して、欠かせないと回答した情報源の割合を、年代別に紹介している。50代以下はインターネットが最も欠かせない情報源と回答しており、例えば18〜19歳では75.7%だが、どの世代も7割を超えている。60代になるとテレビや新聞への回答が高くなる。また、情報源としてYouTubeを利用している人は59%で、そのうち28%はニュースソースとして利用している。YouTubeをニュースソースとしている人は、いろんな世代にまんべんなくいる。ただ、各メディアの信頼度はテレビや新聞に比べてかなり低い。
AIの爆発的な進展の動向
LLMのパラメーター数の推移の傾向を見るため、縦軸にパラメーター数、横軸に開発年月という時系列のグラフを作成した。まず、見えてきたのは大規模化という傾向だ。パラメーターを増やせば増やすほどAIは賢くなるため、どんどん大規模化を進めているという歴史がある。一方で、パラメーター数を抑えたコンパクトなモデルを独自に開発する動きも見られる。AIは世界的に競争が激しくなっているが、スタンフォード大学の研究所が毎年公表しているAI活力ランキングを見ると、やはりアメリカ、中国が圧倒的で、日本は9位と、世界的な評価という意味ではやや遅れている。一方でGENIACという経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によるプロジェクトで、官民挙げて新しい日本独自のLLMを開発しようとしている動きもある。特に、日本語能力をより強化した独自のモデルも公表されている。
そのAI利用について、ウェブアンケートで個人と企業それぞれに生成AIサービスの利用経験を聞いて、日本とアメリカ、ドイツ、中国の4カ国を比較している。さらに、国ごとに2023年度と2024年度を比較した。日本は2023年度の調査では、生成AIの利用経験がある人は9.1%だったが、1年間で約27%と3倍に増えており、AIは急速に普及している。一方で、2024年度ではアメリカは約7割、ドイツでも6割、中国では8割の人がAIの利用経験があると回答している。同じデータだが、日本国内で世代ごとに比較すると20代は45%で、若い人ほどAIに対する抵抗感がない。同じように、企業における生成AIの活用方針策定状況についても国際比較を行った。積極的に活用する方針、あるいは領域を限定して利用する方針と回答をした企業を合わせると、およそ50%になる。これもアメリカ、ドイツ、中国と比べると日本企業は遅れている。
このように日本では他国に比べて、生成AIが個人や企業ともに使われていない理由が知りたくなるところだが、そのヒントになりそうなデータをご紹介したい。個人がテキスト生成AIサービスを利用しない理由は、自分の生活や業務には必要がないからという回答や、使い方がわからないという回答が多い。その「必要ない」というのは、おそらく本当に使ってみたうえで必要ないという人と、使っていないけれど多分必要ないだろうという人が混ざっているだろう。それから、企業に生成AI導入に際しての懸念事項を聞くと、日本では効果的な活用方法がわからないという回答をしている企業が多い。一方で、アメリカ、ドイツや中国では初期コストやランニングコストがかかるなど、コストに関する懸念事項が挙がっている。日本で「活用方法がわからない」という回答を少し悪く解釈すると、検討が本格的に進んでいないため、コストを把握するところまで至っていないという可能性もある。
次に、企業に生成AIの活用により期待される効果、影響について、日本とアメリカ、ドイツ、中国で比較した。日本の場合、業務効率化や人員不足解消につながるという効果を期待している回答が多い。アメリカの場合は、ビジネスの拡大や新たな顧客獲得につながるという回答だ。中国は斬新なアイデアや新たなイノベーションが生まれることを期待している。
デジタル分野におけるその海外事業者の台頭と我が国の現状
ここでは海外プラットフォーム事業者の売上高の推移を紹介しているが、いわゆるGAFAMの売上高と、参考としてトヨタ自動車とNTTを比べると、やはり海外のプラットフォーム事業者の成長は著しい。デジタル関連サービスに関する国際収支を見ると、日本は2024年に6.7兆円の赤字で、これが拡大している傾向が見て取れる。白書には書いていないが、外国人観光客が日本で消費するインバウンドの黒字とこのデジタル赤字が大体相殺し合っている現状だ。赤字額が伸びている理由として、クラウドサービスの利用料や動画音楽配信に伴うライセンス料、インターネット広告への支払いが挙げられている。
財市場について世界的なシェアを見ると、携帯基地局では中国が非常に強い。スマートフォンについてはやはりアメリカとか中国、韓国が強い。PCは、日本は世界シェアの5%になっている。トータルの財に関する輸出、輸入も2024年は3.4兆円の赤字で、やはりスマホを輸入していることによる赤字が大きい。
デジタル分野における海外事業者の台頭と我が国の現状/今後のデジタル社会の見通し
ここまで若干暗い話も多かったかもしれないが、今後の日本の発展を考えていくと、デジタルはやはり欠かせない。世界情勢、あるいは自然環境の変化、人口減少、労働生産性といった課題が山積みになっているが、デジタルの力によってそういった課題を解消できるという期待が高まっているといえるのではないか。一方でデジタルの進展によって、新しい技術の普及に伴う課題が出てきている。総務省を含めて、そういった課題に政策的に対応していかないといけない。
課題として4点挙げている。まず、①デジタル社会を支える信頼性のあるデジタル基盤の確保として、インターネットトラヒックの推移(ダウンロード)を紹介している。現在、トラヒックが加速度的に上がっている。特にコロナの時にビデオ会議などが非常に増えたが、この傾向は現在も変わらず伸び続けている。日本のインフラに対する投資がしっかりできていたため、トラヒックの急増に対応できたとも思うが、生成AIが普及すると、さらにトラヒックが増えることになる。今後データセンター、あるいは急速なデータの流通を支える電力が非常に不足することが指摘されており、これに対してしっかりと投資をしなければいけない。さらに、アメリカ等が非常に強い分野ではあるが、経済安全保障という観点もあるため、日本国内でもデータセンターを持ってやっていかなければいけない。
次に、②AIの進展に伴う新たな課題ということで、やはり日本は利用面において、他の先進国に比べてスタートダッシュが遅れている。とはいえ、AIの利用はハードルが低く、広まり始めれば一気に進んでいくという期待もある。とにかくAIをどんどん使って付加価値を出していくことが大事だ。それから、③インターネット上の偽・誤情報等への対応として、特に選挙や能登地震の際に偽・誤情報が出回るなど、大きな問題になっている。こうした問題にさまざまな手段を使って、対策をとらなければいけない。最後に④サイバーセキュリティの問題は、現在、政府が非常に力を入れて対応している分野となっている。
やはりデジタルは我が国の経済成長、あるいは地方創生、災害対応に非常に期待できる。そういった経済成長や社会課題の解決に向けて頑張っていかなければならないだろう。
写真1 加藤悠介氏
講演2「令和7年版情報通信白書 私の注目ポイント」(庄司昌彦氏)
私が毎年必ず見ている情報通信機器の世帯保有率を見ると、スマホが9割の世帯にある。そこは予想通りだが、パソコンが下げ止まったかというところで約7割。固定電話は今回5.5割で、4.5割の家にはないということになる。スマートフォンの普及は全年代で上がっている。特に見るべきは高齢者で、60代で約8割、70代でも5割以上がスマートフォンを使っている。
また、興味深いデータだが、日本はモバイルブロードバンド大国で、人口100人あたりのモバイルブロードバンド契約数では200を超えている。つまり、2台持ちの人もいるだろうし、おそらく機器に入っていることも含めてだと思うが、モバイルブロードバンドの契約数が非常に多い国である。一方、固定ブロードバンドを見ると、日本は上位ではなくグラフ中央よりやや左、やや多い方の部類にいる。両方のグラフを合わせると、やはりモバイルに特徴のある国だということがわかる。
次に、これも毎年定点観測的に見ているグラフだが、年齢階層別インターネット利用率では60代は9割、70代が7割、80代3割である。そして、コミュニケーション手段としてのLINEの普及は60代までの全年代で9割に達している。
ネットを利用した動画、ラジオサービスの利用率を見ると、YouTubeなどのオンデマンド型動画共有サービスが92%と最も高い。私が注目したのはNHK、民放キー局のオンデマンド型の放送番組配信サービスで、テレビをネットで見る人が増えている。まさに通信と放送の融合だと思うが、これは非常に注目すべきところだと思う。
コンテンツ市場規模は12.58兆円で、グラフを見ると横ばいになっている。ただ、そのコンテンツ市場のうち、パソコン、携帯で見るという通信系のコンテンツは成長しているので、コンテンツ市場内でのシフトが起きていると読むのが正しいと思う。情報収集手段においてもネットが重要な手段になっており、紙の新聞が毎年、主要な手段としてのシェアを下げている。加えてソーシャルメディアによるニュース配信が伸びている。
それから行政系ではマイナンバーカードの普及は、途中で数え方が変わっているが約78%と、8割近くに普及している。税申告でもデジタルが浸透しており、法人税は86%に達し90%を目指している。所得税も80%が現実的な目標になってきている。その他もかなり伸びているということで、行政のデジタル化ではポジティブな数字もある。次に、生成AIサービスの利用は国内の年代別で見ると、20代で44.7パーセントは使っているという回答になっている。ただ、ほかの国と比べると決して高くはないので、全体を底上げしなければいけないが、少なくとも若い人たちには使ってほしい。
加藤さんの話にもあったデジタル赤字は非常に重要なグラフだ。消費電力の増大への懸念ということで、AIの活用が浸透する、あるいは動画サービスなども使われていくことで、データセンターとネットワークの電力需要が2030年まででも相当伸び、2050年には驚異的な伸び率が予想されている。2018年、140億kWhのデータセンターの消費電力が2050年に5000億kWhになり、ネットワークも同じく2018年の18億kWhから2050年に440億kWhになる。このまま行くともっと大変になるという予測になっている。
また、日本の民間情報化投資の差は拡大を続けている。情報通信関連企業の売上高に対する研究開発費の比率では、日本企業は6%か5%である。ところがHuaweiが22.35%、Samsungが10.94%で、GAFAMとBATはApple、Alibabaを除くと10~30%程度あり積極的だ。研究開発費の売上高に対する比率で見ると、やはり日本企業は低い。ただ細かく見ると、Meta、Amazon、Alphabet、Microsoftが比率としては高いものの、ソフトバンクとNTTは2020年代に入ってから研究開発比率を上げていることが見えて、これは良いことではないかと考えている。最後に、民間企業のテレワーク導入率は減少傾向だ。行政、市区町村のテレワーク導入状況も停滞している。残念だが日本はテレワーク、オンライン会議が必要ないという意見が46.7%と顕著に多いが、ほかの国はこんなに高くない。
写真2 庄司昌彦氏
質疑応答
――なぜ民間企業はIT投資を増やさないのか。
加藤:日本市場の将来を考えると、その成長に投資するだけの大規模投資になかなか踏み切りにくいのではないか。最初から海外市場を意識する企業が増えることが大事になる。
――このようなアンケートだと、日本の回答は常に「わからない」が多く、米国、中国はほぼゼロだが、これも国民性なのだろうか。
加藤:やはり日本独特の回答の文化がある。例えば、1から5段階あれば、3を選びがちとも言われる。「わかりにくい」が、判断しにくいのか、知らないのかどちらを意味するのかという日本語独特の難しさもあると思う。また、米国や中国の回答の文化もあるのではないか。
庄司:私はアドバイザリーボードで10年以上見ているが、毎年同じ傾向が続いている。AIに関する意識調査だけでなく、事実ベースの定量的なデータでも分厚く示していくことで、実態と意識の乖離をもう少し描けるようになると良いのではないかと思う。
――デジタル赤字解消のために日本は何をやるべきか。国益という観点でお伺いしたい。
加藤:デジタル赤字が急速に拡大しているのは、ある程度の赤字が安定しているのであれば必ずしも悪いとも言えないが、この傾向が続くのは問題だとは思う。一方で今、日本の企業もAmazonのクラウドサービスを利用していると思うが、色々な企業を比較しても、やはりAmazonの技術力やサービスは抜きん出ているところはある。それを一気に解消しないといけないという話は違うのではないか。クラウドサービスを使っていかに付加価値の高いサービスを作り上げて、それを外国に逆に売っていくことが王道なのだろう。海外を念頭に置いたいろんなサービスを開発することが大事になる。
庄司:今は外資4社がガバメントクラウドをやっているが、今度さくらインターネットが入ってくる。そうやって国産を応援するのは一つの方法ではあろう。しかし、さくらインターネットの田中邦裕社長も話していたが、研究開発投資額が何桁も違うという状況のなかで技術的に太刀打ちするのは、かなり大変だ。おそらくAI開発でも、研究開発の金額に比例して強くなるという部分も大きい。だからこそ、限られた予算でメリハリをつける。ここは国産でやっていこうという部分を見極めて、そこにいかに効率よく投資していくかが重要になると思う。
――若者の生成AIの活用をどう思うか。
加藤:基本的には良いことだと思う。一方で、生成AIに依存するというのは怖い。クリティカルシンキングなり、課題を見つける力をある程度育てたうえでAIを使ってもらわないと、心配もあると感じる。
庄司:私も大学で、あえてAIを使う前提でレポートを出したことがあるが、成績評価は高いレベルの争いになる。安易なAI利用ではいい成績がとれない。このように生成AIを駆使して、よりレベルの高いものを書くという流れになっていくのではないか。
――LLMに関して、国内企業が効果的な使い方がわからないという回答が多くなるのはなぜか。また、それに対してどのような施策を打てばこの傾向が変わっていくか。
加藤:「生成AI=”ChatGPTのようなチャット”」という印象を持っている人がかなり多いのも一つの原因ではないか。「このチャットによってうちの企業はどう変わるの?」という印象を持っている人が多いのではないかと思う。ただ一方で、生成AIの使いどころは個別の業務になるだろう。バックオフィス、あるいは営業とかマーケティングといった個別の業務に導入していくと、目に見える形で効果が現れてくると思うし、そういうことがおそらくここ1年でどんどん広まっていくと思う。そういったことにアンテナを高く張って、いち早く導入していこうというマインドが大事だ。
――デジタル赤字が増えるなか、日本での純国産LLMに期待している。純国産LLMへの期待についてコメントをいただきたい。
加藤:個人的には小規模化に期待している。このまま大規模化がトレンドとして続いていくのかというと、そうでもないだろう。やはり省エネ、あるいは痒いところに手が届く特性といったニーズが広がっていくのではないか。小型化や、職人技を使ってそうしたニーズに合わせたものを作るのは、日本人が得意といわれている分野だと思う。
庄司:私も海外のLLMと組み合わせて使うような、アドオン的なものもあると思う。今、自治体でもそういったものが出てきているが、やはり現場に近い国産は強みがあるのではないか。
――AIのプラス面とマイナス面の両方をバランスよく教育するような動きはあるか。
加藤:他国より利用率が低いが、まずは使ってみるのが本当に大事だと思う。プラス面とマイナス面ということだが、使うことによってだんだん分かってくることことも結構ある。海外でも、AIによって人間の心理や脳の活動にどういう影響を与えるのかという研究も出てきている印象だが、そういったところをよく見極めて、教え方をブラッシュアップしていくことになると思う。
――東京都では「都立AI」という、都立高校生に対してAIライセンスを提供する施策があるが、自治体、家庭の経済格差によってAI活用の格差が広がっていく心配がある。
加藤:具体的に高校生がどれぐらいこの有料サービスを使いこなせているのか現状はわからないが、将来的にはこうした格差が大きな問題になってくるのかもしれない。AIを使いこなせる人はどんどん活用する一方で、AIに触らない人との生産性の差が広がることも起こり得る話だろう。そのため、現時点では、まずAIをうまく使うということを広めていくのが一番重要だと思う。まず、リテラシーをしっかり教えていくことが大事だ。そして、AI以前にいろいろと調べたり、課題を解決したりといった思考力も育てることが非常に本質的なことになると思う。
庄司:私はビジネスで解決することに期待したい。まだビジネスモデルがいろいろ出てくる余地がある。若者に安く良いサービスが提供することができないかと思う。
――かつては家電から半導体分野まで世界を席巻していた日本が、おとなしくなってしまったことが残念。その原因は研究開発費が足りていないからか。将来に向けて現状を反転できる可能性として何が考えられるか。デジタル赤字の解消として国産のサービスの拡充ということだが、太刀打ちできるのか。
加藤:やはり研究開発を縮小してきたことが日本の停滞の一つの大きな要因になっている。AIに関してどんどん巻き返しを図っていただきたいと思うし、海外のように何十兆、何百兆という投資をすることは難しいが、もっと利用に特化するなど、いろいろな道はあると思う。まだまだ反転できる可能性はあるはずだ。デジタル赤字の話についても、いかに日本の強みを見つけて、それで反転攻勢をかけていけるのかということに尽きる。
庄司:白書本体も、ぜひご覧いただければと思う。どうもありがとうございました。
執筆:井上絵理(国際大学GLOCOM主任研究員(併任))