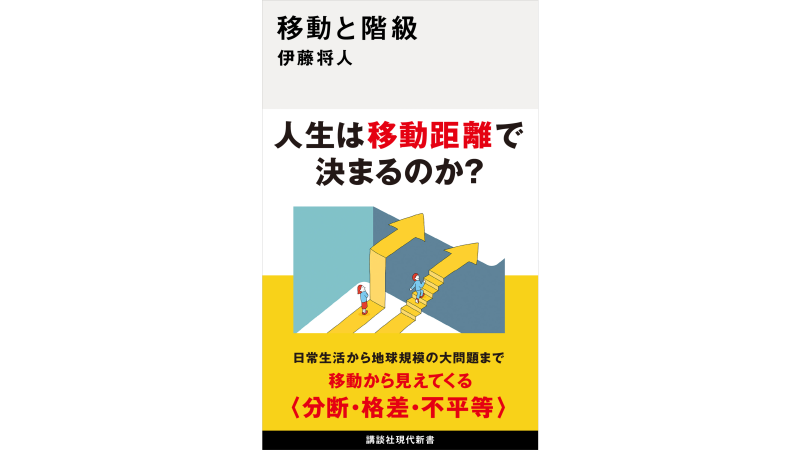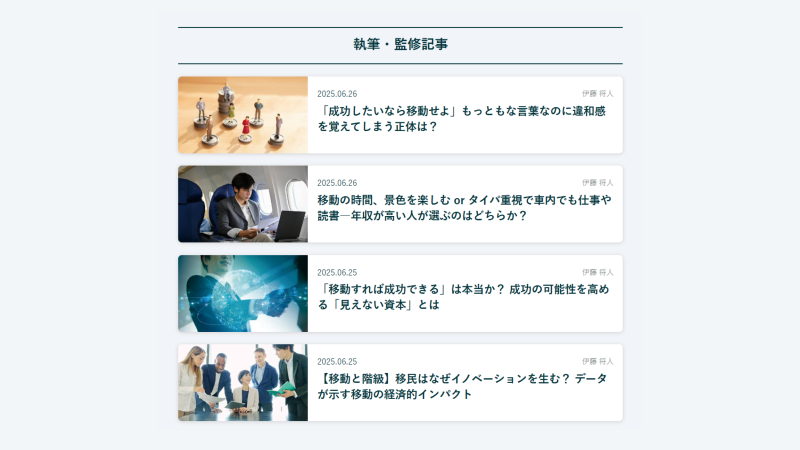講演・パネルモデレーター:
伊藤 将人(国際大学GLOCOM 研究員・講師)
パネリスト:
小田切 徳美(明治大学農学部教授)
稲垣 文彦(NPO法人ふるさと回帰支援センター 副事務局長)
日時 :2025年2月13日(木)18時30分〜20時30分
会場 :国際大学GLOCOMホール
主催 :国際大学GLOCOM
共催 :株式会社学芸出版社
講演「地方移住と移住促進政策の今」(伊藤将人氏)
私は長野県池田町出身で、地域研究と政策学の両視点から移住政策・まちづくり・観光交流を研究している。研究者になる以前から、地域フリーペーパー作成など地域事業に関わり、現在も自治体や事業者と協働して移住政策を実施している。
博士課程以降は地方移住政策史を研究している。1960年代のUターン概念の登場、1980年代の都道府県によるアドバイザー設置、21世紀のIターン概念と国土計画への移住導入、地域おこし協力隊制度、地方創生、コロナ禍といった流れを整理した。「どう移住を促進するか(How to)」を考える前に、「なぜ実施するのか(Why)」を問い直す必要性を強調する立場から、日々、研究と実践を行っている。2024年度に実施した全国3,000人対象のオンライン調査結果は、男女間で移動の自由度の認識に差があること、社会階層や収入によってテレワーク実施率が異なることを示した。また、移動を金銭支援で促すことへの賛否はほぼ半々で、「都市→地方」移住は賛成60.4%、「地方→都市」は25.5%にとどまった。
さらに、同じく2024年度に実施した全国自治体対象の郵送調査では、移住促進の効果を「大きい」とする自治体は55%、「小さい」とする自治体は45%と分かれた。移住促進施策の民間団体への委託割合は、未委託が56%、委託する場合でも地元企業への委託が7〜8割を占め、東京に流出する資金がある一方で、かなりの程度が地域内で資金循環していることが分かった。移住者獲得競争については9割弱の自治体担当者が「高まっている」と回答し、その背景に国の影響を挙げる自治体が多数だった。
以上の結果から、効果的な移住政策に向けて以下3点を提案した。
- 移住者定義の明確化:独自定義を持つ自治体は効果が出やすく、定義がない場合は認識に差が生じる。
- 効果測定と実態調査の強化:移住者の実態調査を行っていない自治体が約7割に留まり、地域に即した実効性ある支援策に向けた更なる調査が必要。
- 移住促進と関係人口促進のバランス:限られた人材・予算の中で、移住促進と関係人口施策促進の重点配分を見極めることが重要である。国と自治体でも方針にはズレが見られるため、自地域の目指す方向性と重ねて考えていく必要がある。
登壇者からのコメント
3名によるディスカッションに移る前に、小田切氏・稲垣氏が本書に対する感想を述べた。
小田切氏のコメント
伊藤氏の博士論文副査を務めた経緯を紹介しつつ、本書は読み切り型でありながら、Part 1で移住の見方、Part 2で多様な移住、Part 3で政策提言という体系的構成を持つと評価し、特にPart 3は「公正」「持続可能」の2つのキーワードを軸に、サステナブルの理念に近い広角的視点で移住を捉えていると指摘した。一方で、結論部分はファクトベースというより「こうすべき」というパッション先行型であるとも評した。
また、課題として、書名に「批判的視点」を反映させてもよかったのではないかという点、移住候補者とプロモーターに焦点を当てている一方、地域サイドの視点がやや薄く感じられる点を述べた。移住と地域の関係性を組み込む場合、どのような議論が可能かを提起した。稲垣氏のコメント
自身が新潟県中越地震の復興支援を17年間続けてきた経験から、本書が「役割やスキルがなくても関係人口になれる」という自らの感覚を言語化してくれた点を評価した。現場では、移住者や関係人口は数より質、すなわち共に喜びを分かち合える仲間づくりが重要であるという感覚を持ってきたが、本書が「量から質へ」「KPIの見直し」を提示した点を高く評価した。
また、議論が「都会が地域を救う」という視点に偏りがちであることに懸念を示し、「地方が都会を救う」という逆方向の視点や、地域と都市の相互利益(ウィンウィン)の関係構築の必要性を提案した。パネルディスカッション
伊藤:小田切先生から「読みやすさ」や「体系性」という点を評価いただけたことを、非常に嬉しく感じている。公正やフェアという言葉については、自身が社会学を研究する中で「移動の正義」や「移動の公正さ」、すなわちモビリティ・ジャスティスの考え方に関心を寄せてきた。経済的豊かさと移動のしやすさが結びつく必要性を強く感じてきたのである。パッションベースとの指摘については、その通りであると認識している。
書名については、移住に関心を持つ層により多く手に取ってもらうことを優先してこの形とした。盛り込めなかった部分については、別の場で論じたいと考えている。地域との関係性については、先行研究を踏まえ、自身のオリジナリティをどこに置くかを検討した結果、政策分野に行き着いた。
また、稲垣さんの「移住者はプロではない」という指摘にも強く同意する。自分自身、かつては地方創生のスキルを備えた高度な人材を目指し、起業して地域や社会を見直すためにフリーペーパー制作などの活動を行っていた。その過程で多くの移住者の声を聞く中、移住者やその活動ばかりが評価され、長年地域を支えてきた地元住民やその活動が十分に評価されていないという現状を知った。この経験が、自身の問題意識の原点となっている。伊藤:お二人にお聞きしたいことがある。地域おこし協力隊制度から15年、地方創生から10年、そしてコロナ禍からも5年が経過した。この間、移住は社会的にも政策的にも関心が高まってきた。その流れの中で、課題点と評価点について意見を伺いたい。
小田切:回答の前に少しコメントをすると、「フェア」というのはプロセスへの評価であり、「サステナブル」というのは結果への評価である。プロセスと結果の双方に触れている議論であった点は、理論的であり納得できるものであった。
さて、ご質問への回答であるが、この10年間の地方創生には様々な問題があった。私自身も批判的な論文を複数執筆してきたが、あえて評価するならば、地方創生は「人」から始まった点である。増田レポートが人口論から出発し、その後、当事者意識を持った人材が地域に入っていくという流れが生まれた。この10年間で、人材への着目という視点が定着したと言える。地域おこし協力隊も集落支援員も、関係人口の一部も、広く「人材」として捉えることが可能である。
課題としては、伊藤さんは移住を交通なども含めたモビリティの一部として捉えている。しかし私は、移住は移住、関係人口は関係人口と分断して捉える現状があると考えており、観光から関係人口、移住、そして永住へと、さらには観光まで含めてシームレスにつなぐことが重要であると考えている。この研究は、モビリティという枠組みでの発展もあれば、そうではない発展の形もあるのではないかと思う。
伊藤:シームレスに捉えるという点は、その通りであると考える。小田切先生と議論をしていると、自身の社会学的な視点が出ていると感じるが、同時に、社会構造の中で目の前の動きがどのような構造から生じているのかを分析する政策学的な視点もある。そのため、二つの視点の間で、どこに比重を置くのかを常にバランスを取りながら研究を行っている。
地域政策に踏み込む際には、関係人口や二地域居住といったテーマにおいても、シームレスな流れの中で実際にどのような政策を打っていくかという段階で、定義の問題が生じる。政策である以上、対象を何らかの形で設定する必要があるが、その設定がどのような規範や前提、価値観に基づくのかが問われる。シームレスであるからこそ区切りが難しく、定義づけに多くの自治体や政策担当者が苦労しているのが現状であると考えている。小田切:伊藤さんには、シームレスな一連の流れを一体的に考えてほしい。これは公共政策という大きな政策領域に含まれると思われるが、現状では適切な名称が存在しない。人と地域のつながりを指す概念としても、政策や都市化といった言葉では表現しきれないため、ネーミングも含めて検討いただきたい。関係人口や観光から移住に至るまでの流れを所管するような部署が市町村内に設置される可能性もあるため、この点はぜひお願いしたい。
伊藤:ありがとうございます。一つ宿題をいただいた。ぜひ後ほどの質疑応答の際に、皆様からもご意見をいただけると嬉しい。この評価点と課題点について、稲垣さんの見解も伺いたい。
稲垣:この10年間で、自治体の取り組みが広がったこと、東京や都市部の人たちが地方に目を向けるようになったこと、企業の動きも出てきたことは大きな成果だと思う。今後も続いてほしい。ただ、東京一極集中はまだ終わっておらず、人の出入りのバランスが取れていないのが現実だ。島根県のように早くから動いた地域では改善が見られる例もある。
自分としては、東京一極集中をなんとかしたいという思いで動いてきた。災害対策の観点からも、「東京にこれ以上人が集まってはいけない」という考えがあり、地方に人を誘導する減災の取り組みをしている。そのため、関係人口の話もどうしても「東京と地方」という構図になりがちだが、実際には地方と地方の間にも重要な関係がある。たとえば近くの中山間地を手伝う場合、東京から行くよりお金もかからないし、子どもたちが地元の大人と触れ合い、子どもも大人も地域への誇りを持つようになる。そうした関係人口は非常に大切だと思う。
移住も同じで、数字としては増えているが、その評価は一様ではない。現場では「隣の家に明かりが戻った」「30年ぶりに子どもが生まれた」というような変化があり、そういう喜びこそ地方創生の本質だと思っている。
一方で、2014年からの地方創生はお金が入り広まったのは良かったが、従来の過疎対策や地域づくりの文脈とは少しずれてしまった感がある。昔から地道に地域づくりを続けてきたところは、この機をうまく生かして好循環を生み出しているが、そうでないところでは齟齬も生じている。自治体ごとの歴史的背景が、移住政策の定義や評価の違いにも影響しているのではないかと感じている。伊藤:稲垣さんの話に関連して、先週訪れた岩手県陸前高田での二つのエピソードを紹介したい。
一つ目は、市の行政や議員の協力で、窓口で継続的に行われているアンケートを分析した結果である。数百件の回答を集計すると、最も多かった理由は「同居・近居」であった。若い世代が結婚や出産を機に親の土地に家を建て二世帯で暮らすケースや、親の介護を理由に戻るケースが多い。こうした傾向は、行政や議員も把握していないことが多かった。
二つ目は、結婚後に地元で暮らしたい、子育てをしたいと望みながらも実現できない人への支援の必要性である。都市と地方だけでなく、地域間移動にも目を向けるべきだが、Iターンが理想とされ東京から地方への移動が重視された影響で、視野が狭まってきた面があるのではないかと考える。
また、1〜2年前の聞き取りでは、震災と無関係に移住する人や、海外志向から国内移住に転じた人も増えていた。理想化された移住像だけでは捉えられない多様な動きがある。
日本の移住政策は、かつてテクノポリスなど産業政策として高度人材確保を目的に推進されたが、近年は地域活性化を重視する地域政策に転換してきた。その結果、かつては、地域貢献は重視されなかったが、現在はスキル・質・地域貢献のすべてが求められるようになっている。
最近は「首都圏在住だが地域と関わりたい」「企業で移住・関係人口促進を担当しているが、収益にならず悩んでいる」という声も多い。都市にいながら地方とつながる、民間だからこそ可能な方法について、稲垣さんと小田切先生の意見を伺いたい。稲垣:「地域に関わりたいが、ビジネスとして求められる形でやろうとするとズレが生じる」という話ですね。私は新潟出身ですが、地元にいるときはあまり気づかなかったことも、東京で働き、さまざまな人と接する中で「そういう考え方もあるのだな」と感じるようになった。農業や流通など、大企業が関わってくれるのは本当にすごいと思いますし、その企業ごとにビジネスや関わり方の形があると思う。ただ、それに対して自分の中で明確な答えを出すというより、「一緒に実現しましょう」というスタンスで関わってきた。
都市で働く人の中には、「豊かさを感じたい」と思いつつも、頭と体が離れているような状態にあって、そこからストレスを抱えている人も多いように思う。自分の物差しを持っていないと、人と比べて豊かさを測ってしまい、より強い人が現れると不安になる。意外なことに、地方移住した人は自分の軸を持ち、豊かさを頭ではなく体で感じているケースが多い。収入は下がったが安心感がある、という声もよく聞く。こうした感覚も含めて、お互いにできることはあるのではないか。
また、都会が地方を救うべきだという視点に偏っている人も多いし、地方のことを知らない都会の人、都会のことを知らない地方の人も多い。関係人口や関係性を深める中で、最終的には地方は力を借りたいのだが、その方法を一緒に考えていければ良いと思う。
伊藤:良いですね。今のお話で出てきた「一緒に」という言葉は非常に重要だと感じる。こちらが一方的に考えて持ち込むのではなく、一緒に考えて、一緒に動くことが大切だ。
稲垣:一緒にできる土壌が整いつつあると感じる。私のところにも相談に来る企業が増えている。まだ共通言語はないが、「一緒に何かしたい」という人は確実に増えており、やっと一緒に考えられるタイミングが来たのではないか。これまでの蓄積も活かせるはず。
伊藤:ありがとうございます。実は今日の参加者の中には、分野を問わず同世代で研究している方々もいますので、お二人から、若手研究者へのリクエストがあれば併せてお聞きしたいがどうか。
小田切:私からの要望はほとんどない。私は海外の途上国や先進国を、日本の農山村とほぼ地続きのものとして捉えている。かつて世界を放浪する人々が一定数存在し、「最近の若者は内向きになった」と言われることもあったが、実際にはその一部が日本の農山村に向かっていると考えている。それは非常に頼もしい傾向であり、近年はますます強まっている。私のゼミ生というと大きなバイアスはかかるが、夏休みにはほとんど東京におらず、彼らに会うためには私が地方に赴かなければならないほどである。
したがって、特段の要望はなく、研究を志すのであればその延長線上で進めてもらえばよいと考える。企業との協働については、視点を少し変えて「人」に焦点を当てたい。外部サポート人材の流れを見ると、2008年に総務省の集落支援員制度、2009年に地域おこし協力隊制度が始まり、その後も外部人材は多様化を続けている。企業に関しても、企業版ふるさと納税など制度やメニューが次々と増えており、先月から始まった農水省のプラットフォームも、そのような場を創出しようとするものである。
現段階で必要なのは、企業ごとの「何ができるか」の棚卸しである。ある企業は資金提供、ある企業はボランティアや労働組合との協働など、それぞれの強みがある。その棚卸しの後、制度に結びつけて実現する段階では、コーディネーターや外部サポートの専門家に任せるべきである。企業側が「これができる」と整理し、その後の実行部分を専門家に託せば、提供できるメニューはさらに拡大していくであろう。伊藤:ちょうど来週、この場で企業向けに関係人口について講演する機会があるため、本日のお二人の意見もそこで紹介したい。先ほどの調査結果にもあったように、外部委託の事例や、移住後に受託側となって当事者の経験を活かし地域政策に関与する動きなどを多く目にしている。今後は研究者の立場からも、その実態を継続的に把握していきたいと考えている。
会場参加者からの質疑応答
――ふるさと住民登録による関係人口の可視化をどう考えるか。
小田切:関係人口は可視化が難しいため、制度化によって見える化できる点に意義がある。また、関係の離脱を抑える効果も期待でき、今後の議論の土台になりうる。
伊藤:数値はエビデンスとして扱われるため、推計は慎重であるべきだ。まずは小規模に試行し、ニーズと規模感を把握すべき。Uターンに至らずとも地元とつながりたい層を適切に把握・支援する仕組みとなる可能性がある。
稲垣:専門ではないが、災害復興の観点では「頼れる人がいる」価値は大きい。地域と関わる機会が増えるなら前向きに進めるべきである。
伊藤:重要な視点である。
――地方のまちづくりは困難であり、空き家は増加し、交通改革も難航している。日本では地方から優秀な人材が東京に流出し、地方都市に人材が不足しているため、再び人が地方に移り住むことで状況が変わるのではないかと考える。本書を通じ、移住や関係人口について理解が広がり、少しでも行動の変化につながることを期待する。
伊藤:空き家については、移住の際に田んぼをつぶして新築を建て、結果として空き家が増えることは望ましくない。将来に向け、田園など景観としての価値を維持しつつ受け入れを進めることが望ましいと考える。
小田切:都市構造を欧米と比較して考えると、地方自治の要素は極めて重要である。日本は総合的行政主体としての地方自治体を有しているが、その地方自治体に加え、中間支援組織や所属するエキスパートの存在も不可欠である。地方自治体を中心に据え、新たに組み立て直す発想が必要である。
稲垣:列島改造で道路や新幹線などのハードインフラは整備されている。これに加え、移住コーディネーターや関係人口の窓口といったソフトインフラを整えることで、既存のハードインフラをより活用し、交流を活発化できる好機であると考える。
伊藤:コロナ禍で普及したテレワークやリモートワーク環境を維持することは、住む場所の自由や選択肢を広げるという意味で非常に重要である。政策や地域だけでなく、企業がテレワーク等の制度を整えることで移住促進に貢献できるという点に大きなヒントがある。また、韓国など東アジアの研究者に移住や関係人口の概念が広がっており、五カ国の研究者による比較研究の動きも我々の世代で始まっている。今後も積極的に成果を発信していきたい。
――IT企業で勤務しているが、本書に出てくる「転職なき移住」という概念に関連し、逆に「移住なき転職」や「移住なき就職」を我々は考えがちである。これは地方創生の文脈において企業として実施してよいのか、あるいは考え方を修正すべきなのか、どう捉えればよいかアドバイスがほしい。
伊藤:地方で話を聞くと、地元にいてほしいという気持ちと、一度外に出て経験を積んで視点を相対化してほしいという気持ちの双方があるとよく耳にする。個人的には「転職なき移住」について批判的な視点を持ちつつも、二項対立で捉えるのではなく、GLOCOMが提唱するようにテクノロジーを活用し、柔軟に可能性を広げていくことが望ましいと考える。
小田切:特定の都市にずっと居続ける必要はなく、ライフステージに応じて地方や都市を行き来する自由を妨げないことが重要である。その意味で、都市に居住しつつ場合によって農村や地方の仕事に関わることは人口移動の一形態である。ただし、その際に問題となるのは依然として存在する格差であり、対等な条件下での選択になっていない点である。現状の研究に加え、都市と地方の格差を是正する研究を同時に進めることが望ましい。
稲垣:現在の移住は若者や意識変化の影響もあるが、その背景を支えているのはテクノロジーの力である。かつては移住すれば友人関係が途絶えたが、今は維持できる。宅配などで物資も迅速に届くなど、テクノロジーが移住を後押ししている。また、地方人口の問題に関して、若者を地方から出さないという発想はやめるべきであり、多様な世界を経験したうえで帰ってこられる環境を整えることが重要である。現場経験は将来につながることが多く、テクノロジーを通じて多様な世界を体験し、多様な幸せや楽しみが存在することを都会の子どもたちに伝えることで、未来は変わっていくと考える。
登壇者からの最後の一言
伊藤:自著には書けなかったが、商工会の青年部などで「自分たちは地方創生に貢献できていない。どうすればよいのか」というテーマで話す機会が何度かあった。実際には、彼らは地域を維持し、雇用を創出し、家族を持ち、消防団やPTAにも参加している。それにもかかわらず、地域活性化に関わっていないという感覚を抱かせてしまうのであれば、この10年、20年にわたり地域活性化や地方創生で語られてきた理想像が現場の実態とずれている可能性がある。これは移住にも当てはまる。行き先の地域に人が住み、電気が灯り、田園が広がっているからこそ移住したいと考えるのであり、そこに暮らす人々へのリスペクトと敬意を忘れてはならない。この点は強調してもしすぎることはないと考える。
稲垣:本日はありがとうございました。今の話の延長として、地域づくりにおいてはいきなり課題解決を目指しても実現は難しい。東京のスキルを持って地方に入り、即座に解決を図ろうとしても拒否されるだけである。まずは関係性を構築し、主体形成を行うことが重要である。時間はかかるが、異なる世界の人々が互いに学び合うことで主体形成が可能となる。そのうえで課題解決に進むという順番を誤ってはならない。これは伊藤さんの話とも通じるものであり、この主体形成の過程を社会的インパクトとしてどう評価するかが問われている。主体形成によって考え方が変わらなければ、その後の社会課題の解決や経済成長、人口増加にはつながらない。このプロセスの評価方法について、皆で議論を深めていきたい。引き続きよろしくお願いします。
小田切:このような場を設けていただき、大変嬉しく思う。楽しく参加させていただいた。研究の世代交代を意識し、三点申し上げたい。私はこの分野で移住を「田園回帰」と呼んできたが、これを三つに整理できる。第一は人口論的田園回帰、第二は地域づくり論的田園回帰、第三は都市農村関係論的田園回帰である。今回、伊藤さんは第一の人口論的田園回帰について、移住の全体像をまとめ、体系的な書籍として提示したと評価している。今後は第二にあたる「移住者がいることで地域はどう変わったのか」という視点、さらに第三の「移住によって都市と農村の関係がどう変わったのか」という国土的視点も必要になる。移住・田園回帰研究にはこのような深みがあり、あと二層の課題が残されている。ここも含めてバトンを渡さなければ、私は死ねないと考えている。引き続き尽力されたい。
執筆:小杉亮太(一橋大学 大学院社会学研究科 博士課程)